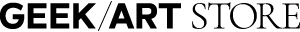陶芸家・阿部寛史「不完全さと静かな抗い」
私たちは、いつの間にか均一で、完璧な形の器に囲まれて暮らしている。傷も歪みもなく、どれもが同じように整った“かたち”たち。けれど、その整いすぎた世界の中で、一点ものの陶器を——あえて暮らしの中に置くとは、どういうことなのだろう。 今回は、陶芸家・阿部寛史の作品を通して、その意味を探っていきたい。Text: Masato Takahashi Photo Assistant: Izumi Mochida 10代というトンネルの中で 十代は、繊細で儚く、不安定なトンネルを駆け抜けるような時期だ。阿部にとっても、それは例外ではなかった。葛藤と模索のなかで高校を卒業し、公務員を志して千葉の短大へ進学。そこでの出会いが転機となり、美大進学を目指すようになる。 「十代の、その頃の苦しみと喜びの感覚は、今でも自分の原動力になっています」 山形で見つけた静けさ 人口が少ないぶん、街には広告も少ない。欲しくないものを“欲しがらされる”機会も減った。「東京は同調圧力を強く感じてしまって、生きづらかったです。山形は人が少なく、静かに考える時間が増えました」 いま阿部は山形に拠点を置き、この土地で陶芸を続けていくつもりだ。20代半ばの彼は、繊細さと脆さを抱えながら、自分の軸を少しずつ築き上げている。 桃山茶陶と「見立て」 現在、阿部は桃山の器の写しを制作しながら、その研究を続けている。過去から学び、それを引き継ぎ、現代に蘇らせようとしている。 「桃山茶陶を通して最も伝えたいのは、そこにある見立ての感性です。見立てとは、本来の用途と異なるものを、別の価値に置き換えて使う、日本の美意識に深く根付いた考え方です。たとえば、料理を盛る器をお茶碗として使うような、固定観念にとらわれない発想です」 この『見立て』という感性は、当時の時代背景とも深く結びついている。桃山時代は、戦乱が続く混沌の時代だった。今日の味方が明日の敵になるような不安定ななかで、人々は完璧さではなく、不完全さの中にある美を見出すようになった。 華美で均整のとれた輸入品よりも、歪みやひびのある土の器を尊ぶまなざしは、当時の権力者たちが競い合っていた華やかな美意識へのささやかな反発であり、権威や富が象徴する“完璧さ”へのアンチテーゼであり、同時に——静かなカウンターカルチャーでもあった。 阿部は、この見立ての精神に強く共鳴している。見立てとは、一点ものに宿る個の力を見つめ直す行為でもある。ものの見方を少しずらし、新しい価値を立ち上げる。それは時代に抗う静かな美学であり、他人の価値観に流されず、世界を自分の物差しで見直すための感性でもある。 温故知新 そして今、均質で整いすぎた世界を生きる私たちにも、その精神は問いかけてくる。同じ基準で測られることが安心だと錯覚し、気づかぬうちに他人の物差しで生きてしまうような時代に—— 自分の物差しを持って生きられているだろうか。 阿部は過去から学び、その物差しを手に入れようとしている。 私たち自身もまた、いびつな“一点もの”として生きている。その歪みを抱えながら、同時に他者のいびつさや違いをも受け止めること。「見立て」というまなざしは、想像力を育み、想像力はやがて寛容さへと変わっていく。手でつくられた陶器には、そんな力が宿っているのかもしれない。 阿部寛史 GEEK ART STORE. こちらでの展示作品は、以下よりご覧いただけます。ご購入も可能です。INSTAGRAM @abe_hiroshi_toge 1999年生まれ 東京都出身、山形県在住。令和の桃山再考をテーマに、安士桃山時代における茶の湯の思想と美意識をもとにした作陶を行う。陶芸に取り組む以前は線画での無意識的な線の模索をしていたが、桃山に無作為の美を感じ、古陶再現に取り組むようになる。異文化交流や禅の思想が花開いた桃山時代の茶陶に込められた精神性は、多様な価値基準が行き交う現代において自己を見つめ直す手掛かりになると考える。現在は古陶の再現(写し)とその差異を軸に令和的桃山陶のかたちを模索している。