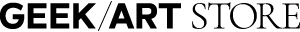アーティスト・大根マリネ「ユーモラスに問い直す美術史の不均衡」
Artist Marine One: "A Humorous Reexamination of the Imbalances of Art History"
私たちが生きる社会は、目に見えない無数のコードによって形づくられている。美術史はそういった社会のあり方を反映し、長きにわたって様々な女性像を作り出してきた。その一方で、同じように社会的コードをまとう「男性性」のイメージは、どのように再認識され得るのだろうか。
Our society is shaped by countless invisible codes. Throughout history, artists have depicted women's bodies, with evolving artistic styles reflecting each era’s societal views on femininity. How, then, might we examine artistic portrayals of ‘masculinity’, likewise culturally embedded but presenting in such contrast?
インタビュアー/ライター: Yuki Saiki
Interviewer/writer: Yuki Saiki
日本に生まれ、国際的な美術教育を経て活動するアーティスト・大根マリネ(Marine One)の作品は、「有害な男らしさ(toxic masculinity)」という政治的主題を、あえてぬいぐるみのようなテキスタイルとユーモアで包み込む。本インタビューでは、社会の中に無意識に根付いた「男性の表象」のあり方を覆す試みについて探る。
Born in Japan and educated in Europe, artist Marine One wraps the political theme of “toxic masculinity” in plush, toy-like textiles and humour. In this interview, we explore her attempt to challenge and overturn unconsciously embedded representations of masculinity.

国境を越えて形成されたファインアートへの視点
A transnational perspective on contemporary art
大根マリネがアーティストを志したきっかけは、幼い頃から漫画に親しみ、工作をしたり絵を描いたりと、自分自身の手を動かして何かを作ることに喜びを見出していたことに始まる。また、8歳の時に父と訪れた原美術館で鑑賞した束芋「ヨロヨロン」展には特に衝撃を受け、現在の制作にも通底する「不可思議な感覚」の原体験となったという。
「10年後に美術を本格的に学び始めて、自分がどんな作品をつくりたいか考える中で、あのとき受けたショッキングで不可思議な感覚を生み出す作品をつくりたい、と思いました。それと、この自身の体験から、子供がアートに触れることの重要さも実感しています。」
Marine’s motivation to become an artist stems from her childhood love of manga, crafting, drawing, and the joy she found in making things with her own hands. At the age of eight, she visited the Hara Museum of Contemporary Art with her father and was deeply struck by Tabaimo’s exhibition Yoroyoron, which she describes as a formative encounter that shaped the “mysterious sensation” underlying her current practice.
“Ten years later, when I began studying art [in a university setting], I thought about the kind of work I wanted to make. I realised I wanted to create something that could evoke the same sense of shock and mystery I felt back then. That experience also made me understand how important it is for children to be exposed to art.”

さらにアーティストとしての方向性を決定づけたのが、イタリアの国立美大での経験だ。受験や就職など他者との競争にさらされる日本の大学システムとは違い、イタリアの大学では座学や絵画技術等の必修科目の他は自身が興味のある分野を自由に学べたという。のびのびとしつつも自身の内面と真剣に向き合わなければならない環境の中で、大根は自分が表現したいことを最も自由に追求できる媒体がファインアートであると確信した。さらに、ミラノのHangar Bicoccaでルーチョ・フォンタナのインタラクティブ・インスタレーションに感銘を受けたことで、鑑賞者が直接触れ、体験するアートへの関心が深まったという。
さらに、修士課程ではイギリスのセントラル・セント・マーチンズ(CSM)へ進学。ロンドンという国際色豊かな都市で様々な文化・政治背景に触れた経験は、自身の視点を広げる大きな糧となったという。
Furthermore, Marine’s time at Accademia di Brera in Milan played a decisive role in shaping her artistic direction. Unlike the Japanese university system, where students compete through entrance exams and the pressures of job hunting, the Italian system allowed far greater freedom. Alongside required courses such as art history lectures and painting techniques, students were free to explore areas that genuinely interested them.
Within this more relaxed environment, students were encouraged to reflect seriously on their inner selves. Marine said this phase of life reinforced her belief that fine art was the medium that offered her the greatest freedom to express her ideas, and decided she wanted to reach people through immersive art. She said her interest in experiential art deepened further after encountering Lucio Fontana’s interactive installation at Hangar Bicocca in Milan.
She later completed a master’s degree at Central Saint Martins (CSM) in the UK. She says that being immersed in the diverse cultural and political spheres of London’s international art scene greatly helped her to broaden her perspective and deepen her work.

「ニュートラルなオブジェ」として捉えなおされる男性像
Masculinity reconsidered as a neutral object
大根は大学時代から、「自分が気づかないまま吸収している偏見」や「無意識下での自己認識の形成」に興味があり、中でも性別という要素が持つ大きな影響力から、ジェンダー、特にフェミニズムについて研究していたという。当初は女性の身体を使った作品を制作していたというが、美術史上では既に多くの女性の身体が描かれていることを意識する中で(*1)、男性の身体を表象することへの関心が高まった。大学院では作品と鑑賞者の関係性を研究し、男性の身体とMale Gaze(*2)を結びつけた作品をつくり始めたことをきっかけに、男性性そのものに関心が移っていった。これは「いわば、女性の身体と同じように、男性の身体もニュートラルなオブジェとして提示し直す試み」であるという。
「いわゆる有害な男らしさ(toxic masculinity)は女性だけでなく、男性自身にも負担をかけているにもかかわらず、社会に深く根付いたままです。その違和感や矛盾を、自分の作品の中でユーモアを交えながら扱ってみようと、制作を続けています」
大根の作品に登場する人物の服装には、サラリーマンを象徴するスーツ姿やホモソーシャルを擬人化したような男性像など、一般的に美術作品ではあまり見かけないような人物像が登場する。しかし、登場人物たちの装いはキッチュで過剰な雰囲気を持ち、どこか滑稽さすら漂っている。この背景には、社会的な役割やイメージを象徴する服装を取り入れることで、男性性にまつわる文化的・構造的なコードを浮かび上がらせ、美術においてあまり表現されてこなかった「誇張された男性性」を表現したいという思いがあるという。
私たちに身近な社会的コードをまといながら、布という親しみやすい素材によって提示される大根の誇張された男性像は、固定観念にとらわれた社会構造に対するユーモラスなカウンターであると言えるだろう。
During and since her time in university, Marine has been interested in "prejudices we absorb without realising" and "the formation of unconscious self-awareness." She takes particular interest in discussions around gender and feminism, which have played a significant role in shaping her thinking. She initially created works using the female body, but as she became aware that the female form has already been extensively represented throughout art history, her interest gradually shifted towards the depiction of the male body.
In developing her practice, Marine has explored the relationship between artwork and viewer. As she began creating works that linked representations of the male body with the concept of the male gaze, her focus turned towards masculinity itself. She describes this as “an attempt to re-present the male body as a neutral object, in the same way the female body has long been the go-to muse.”
She is particularly interested in the softer, gentler side of masculinity, and exploring the forces that turn men away from this toward ‘toxic’ or harmful expressions. “Everyone suffers under cultures of toxic masculinity, men in particular, yet it remains deeply rooted in society. I hope to address this discomfort and contradiction in my work, with a touch of humour so people can see the lightness there could be.”
The characters in Marine’s works often appear in clothing not typically found in art, such as business suits symbolising salarymen, or male figures embodying forms of homosociality. Yet their clothing is intentionally kitsch, excessive, and even humorous. This approach reflects her desire to expose cultural codes we may otherwise rarely consider, and to highlight the outlandishness of certain societal expectations of men. She incorporates garments that symbolise social roles and stereotypes, and express an “exaggerated masculinity” that has seldom been depicted in art. Marine’s exaggerated images function as humorous counterpoints to stereotypes, flipping expectations on the head.
(*1) 美術における性別間不均衡を批判した事例としては、ゲリラ・ガールズ(Guerrilla Girls)は、Do Women Have to Be Naked to Get into the Met. Museum? (1989)において、「美術館におけるモダンアート部門のうち女性アーティストは5%未満であるのに対し、ヌード絵画の85%が女性である」という統計を掲げたことなどが挙げられる。
Examples of gender imbalance in the arts include the Guerrilla Girls’ Do Women Have to Be Naked to Get into the Met. Museum? (1989) highlighting the statistic that 'less than 5% of the artists in the Modern Art Sections are women, but 85% of the nudes are female’.
(*2) 女性の身体が男性の欲望の対象として描かれるなど、鑑賞者が「男性的な」鑑賞姿勢に立つように視覚芸術の対象をフレーミングされる仕組みを指す言葉。
A term that refers to the structure in which visual art is framed in a way that positions the viewer in a "masculine" mode of looking, such as when the female body is depicted as an object of male desire.

テキスタイルがもたらす「ズレ」と「違和感」
The “misalignment” and “discomfort” produced by textiles
また、大根は作品の素材に布やビーズを使用していることも特徴的。布を素材として選択することについては「大きい作品以外は型紙などをしっかり計算して作っているわけではないので、縫っていて計画通りに行かなかったり、立体に起こす際予想と違った形になることも多々あります。でもその”ずれ”が次の作品の参考になったり、自分の計画より面白い方向に進むことが多いので、そういったフレキシブルさが好きです」と語る。
布という素材の柔らかさに加え、意識的に明るい色を使ったり、作品の雰囲気にそぐわないアイテムや小物を混ぜたりして「ちょっとしたズレ」をつくる。このことが、大根の作品を「怖いだけじゃなくどこか笑える、変だけど気になるという感覚が生まれる」ものへと昇華している。大根は「私自身が、違和感とユーモアのある作品を見るのが好き。つまり、自分が見たいと思う作品をつくっている、という感覚に近いです」と語る。
さらに、素材の選択はフェミニズムやジェンダーという制作主題とも深く関わっている。「テキスタイルやビーズワークは、美術史の中で長く女性の手仕事や工芸として軽く扱われてきた背景があります。男性性を扱う作品であえてその素材を使うことに、歴史的な文脈も含めて面白さを感じています」
Another distinctive feature of Marine’s work is her use of fabric and beads as primary materials. Speaking about why she chooses fabric, she explains: “Except for the larger pieces, I often make things freely instead of calculating the patterns, so there are many moments when the sewing doesn’t go as planned. Often a piece becomes three-dimensional and ends up taking on a different shape from what I had imagined. But these deviations become reference points for my next work, and they often lead in more interesting directions than I had originally expected. I enjoy that kind of flexibility.”
In addition to the softness of fabric, Marine intentionally uses bright colours and incorporates items or accessories that feel slightly out of place to create a sense of “slight shift.”

大根はジェンダーや身体をめぐる政治を作品の主題とする一方で、インタラクティブな作品において鑑賞者が質感を直接楽しめる布を使用することで、ぬいぐるみのような親しみやすさや遊べる感覚を残している。違和感や気味悪さを表現することが多いぶん、作品の視覚的な印象と触覚のギャップを楽しんでもらいたいという。
「私の作品は第一印象がどこか気持ち悪い方向に寄りがちです。でもそのままダークになりすぎないように、必ずどこかに抜け感やユーモアを残すようにしています」
This quality elevates her work into something that “isn’t just frightening, but somehow funny; strange yet compelling.” She adds, “I personally enjoy works that feel odd and humorous. In a way, I’m making the kind of work I would want to see myself doing.”

大根は現在ロンドンを拠点とし、The Bomb Factory Art Foundationに所属している。同じスタジオに所属する仲間とスペースをシェアしながら、作品について話し合ったりアイディアを出し合ったりしながら制作する環境は、新しい発想を得る上で非常に重要だという。
12月には、The Bomb Factory Art FoundationのArchwayスタジオにて、「抽象的なぬいぐるみ」を制作するワークショップを企画しているという。「型紙を作らずに自分のスケッチだけを参考に、立体のぬいぐるみを作ろうというものです。平面から立体に起こす時の考え方、様々な素材の組み合わせを楽しむワークショップです」
Marine is currently based in London and is affiliated with The Bomb Factory Art Foundation, with her studio in Archway. She says that the environment in which she works, sharing a space with fellow studio members, discussing each other’s work, and exchanging ideas, is extremely important for generating new perspectives and new ideas.
In December, she is leading a workshop on creating “abstract stuffed animals” at The Bomb Factory Art Foundation’s Archway studio. “The workshop involves making three-dimensional stuffed animals using only your own sketches as reference, without creating any patterns. It’s an opportunity to enjoy the process of figuring out how to transform something flat into a three-dimensional form, as well as experimenting with different combinations of materials.”
In short, Marine’s work, which weaves together darkness and humour, can be seen as a soft yet incisive inquiry into the rigid social structures that shape our daily lives. We hope you will continue to follow her unique art and future work.